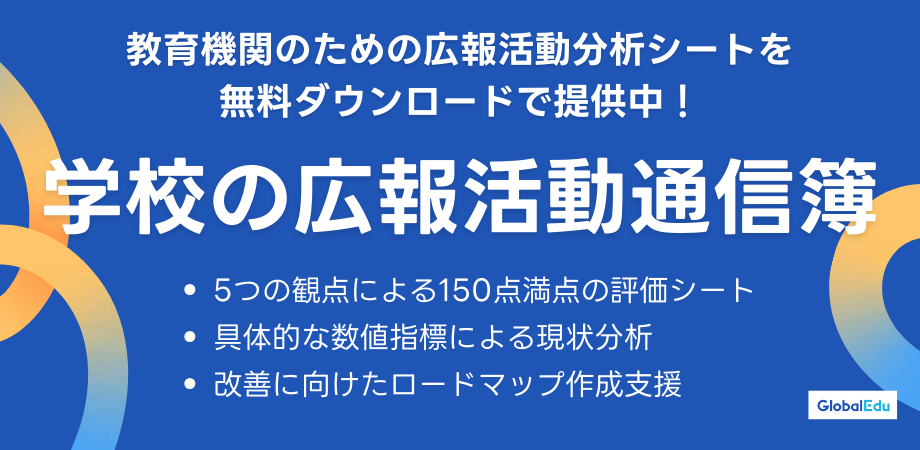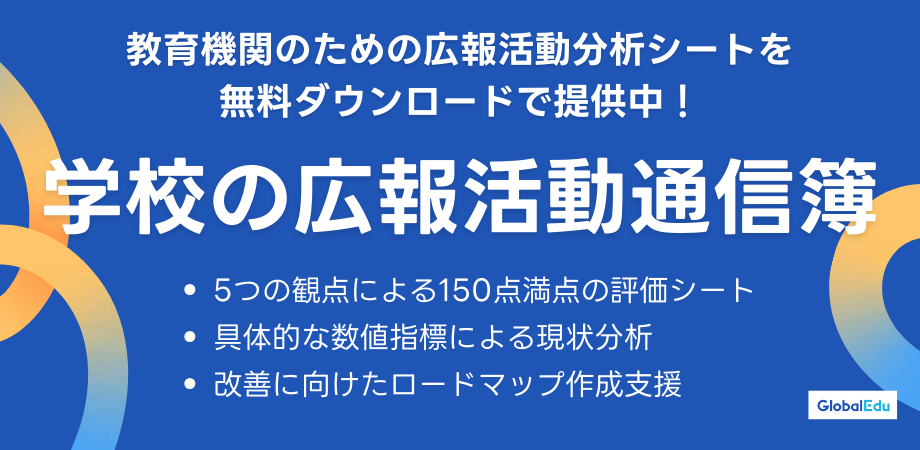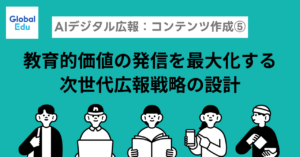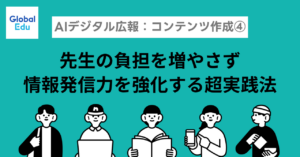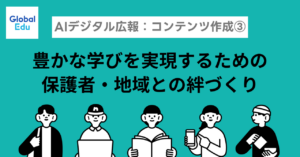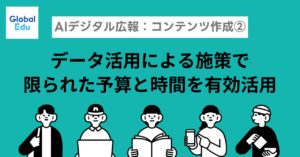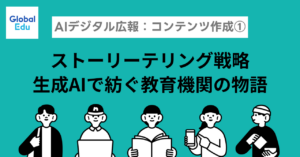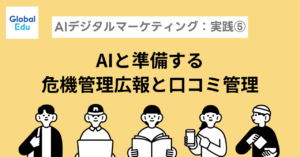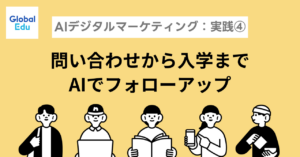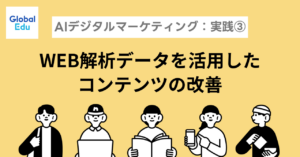Globaleduメルマガでは、広報担当者のみなさんの日々の仕事に役に立つ情報をお届けしています。ぜひご登録ください!
教育機関の広報:実践④デジタル時代にこそ!魅力的な広報誌制作ガイド
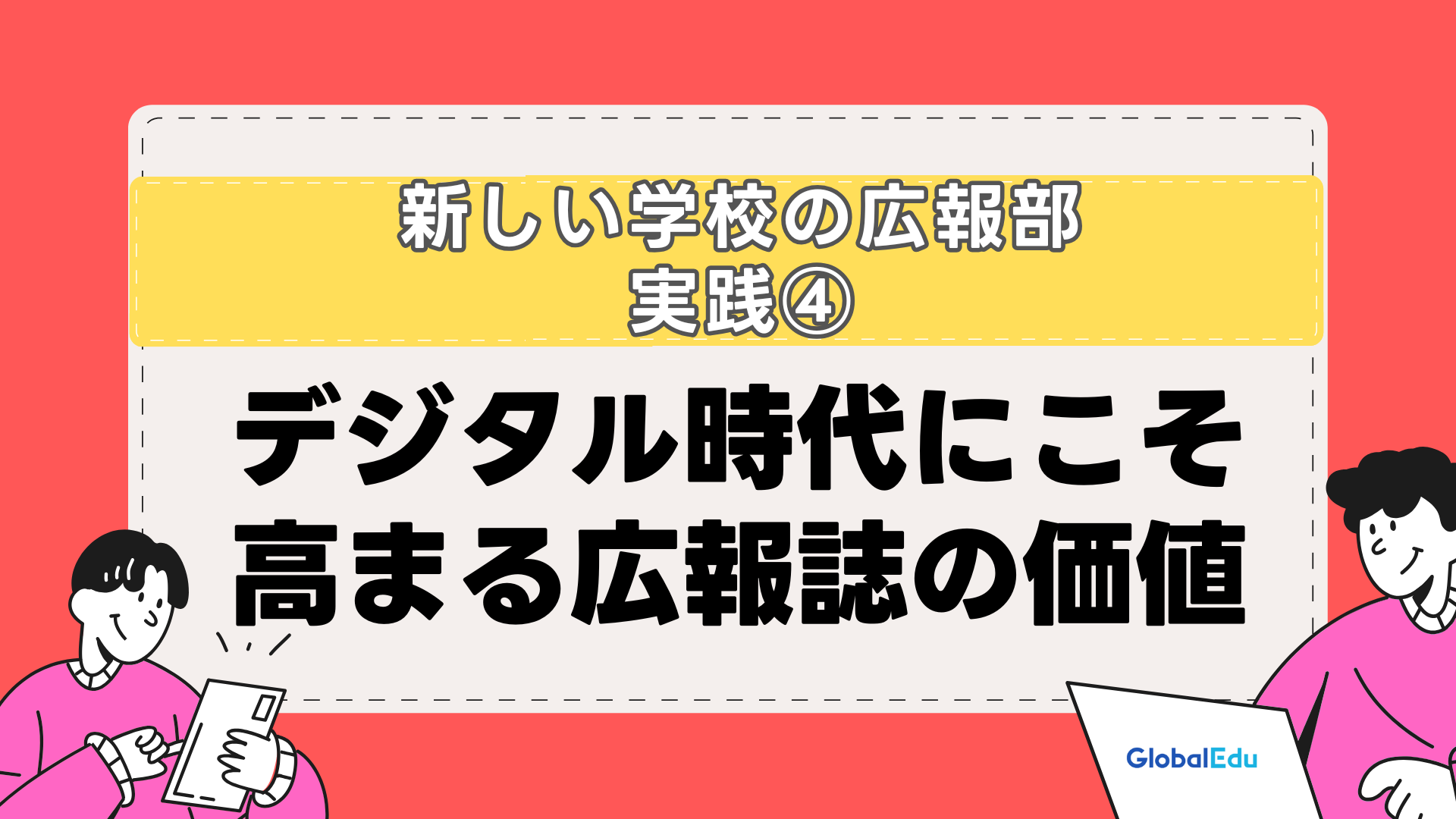
\ 本特集の広報施策を自己評価・分析できる /
なぜいまこそ広報誌が重要なのか
教育機関の広報活動において、広報誌は依然として重要な役割を果たしています。
 広報担当Aさん
広報担当Aさんたしかに、SNSやWebサイトが主流となった現在でも、手に取って読める紙媒体には独自の価値がありますね〜!
とくに、保護者や地域住民の方々にとって、広報誌は学校の活動を知る重要な窓口となっています。



この記事では、はじめて広報誌制作に取り組む担当者に向けた、基本的な知識をお伝えしていきます
効果的な広報誌の企画とは
広報誌の成功は、企画段階で8割が決まると言っても過言ではありません。「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを明確にすることが、読まれる広報誌づくりの第一歩です。
テーマ設定では、学校の魅力を効果的に伝える切り口を見つけ、読者層に合わせた内容と表現を工夫します。
一度立てた企画に固執せず、企画会議での議論を通じてブラッシュアップしていくことが重要です。
テーマ設定
各号のテーマは、スクールのブランド価値を高める内容を選びます。
- 特色ある教育活動の深掘り
- スクールスタッフの思いや取り組み
- 子どもたちの成長ストーリー
- 地域との連携事例 など
ターゲット設定
読者層を明確にすることで、内容や表現が具体的になります。
- 在校生の保護者
- 入学希望者とその保護者
- 地域の人たち
- 卒業生
誌面構成のポイントを考える
広報誌の誌面構成は、読者を惹きつけ、最後まで読んでもらうための重要な要素です。
表紙は広報誌の「顔」として、インパクトと親しみやすさのバランスが求められます。
また、特集記事、学校生活レポート、コラム、お知らせなど、読者の関心に応じた記事を適切に配置することで、読みやすく、魅力的な誌面が実現できます。
文字の大きさ、写真の配置、余白のバランスなど、視覚的な要素も配慮しましょう。
表紙デザイン
もっとも重要な「顔」となる表紙は、以下の要素を意識します。
- インパクトのある写真や図版
- 読みやすい見出し
- 統一感のあるデザイン
- 季節感の表現
基本構成
一般的な広報誌の構成例をあげてみます。
- 巻頭特集(4〜6ページ)
- スクール生活レポート(2〜4ページ)
- スタッフコラム(1ページ)
- お知らせ・行事予定など(1ページ)
制作プロセスとスケジュール
広報誌の制作は、企画から発行まで約2ヵ月のスケジュールで進行するといいでしょう。
企画会議でテーマを決定し、取材・原稿作成、デザイン・レイアウト、校正・確認、印刷・発送と、段階を追って進めていきます。
各工程での遅れは後工程に大きな影響を与えるため、計画的な進行管理が重要です。とくに校正・確認の段階では、複数の目でチェックを行い、誤りのない誌面づくりを心がけましょう。
①企画会議(発行2ヵ月前)
- テーマの決定
- 担当者の割り振り
- スケジュール確認
②取材・原稿作成(1.5ヵ月前)
- インタビュー実施
- 写真撮影
- 原稿執筆
③デザイン・レイアウト(1ヵ月前)
- ラフレイアウト作成
- デザイン方針決定
- 写真選定
④校正・確認(2週間前)
- 内容確認
- 誤字脱字チェック
- 関係者確認
⑤印刷・発送(1週間前)
- 印刷仕様の最終確認
- 部数の確認
- 配布リストの更新
読まれる広報誌の3つのポイント
広報誌が読者の手に取られ、最後まで読まれるかは、視覚的な工夫、文章表現、企画内容の3つの要素にかかっています。見やすいレイアウト、読みやすい文章、魅力的な企画の組み合わせが肝になります。
さらに、読者目線での情報提供を心がけ、「スクールが伝えたいこと」と「読者が知りたいこと」のバランスを意識しながら、コンテンツを構成していきましょう。
①視覚的な工夫
- 大きめの写真使用
- 適度な余白
- 読みやすい文字サイズ
- メリハリのある見出し
②文章表現
- 簡潔な文章
- 具体的なエピソード
- 数字やデータの活用
- 親しみやすい表現
③企画の工夫
- 生徒・スタッフの声の活用
- 連載企画の設定
- 読者参加型のコーナー
- アンケート結果の反映
予算管理とコストを削減する方法
限られた予算で質の高い広報誌を制作するには、印刷コストと制作コストの両面からの管理が必要です。
部数や用紙の選定、印刷方式の検討など、印刷に関わるコストを最適化しつつ、テンプレートの活用や写真・原稿の内製化など、制作プロセスの効率化も重要です。



ただし、過度なコスト削減は品質低下につながる可能性があるため、読者に届ける価値とのバランスを常に意識しましょう
印刷コストの管理
- 適切な部数設定
- 用紙の選定
- 印刷方式の検討
- 発送方法の工夫
制作コストの効率化
- テンプレートの活用
- 写真の内製化
- 原稿の内製化
- デザインの標準化
効果測定と改善のコツ
広報誌は発行して終わりではありません。読者アンケートや感想収集を通じて、企画内容や表現方法が読者のニーズに合っているか、定期的に確認することが重要です。
とくに気をつけたいのは、読者の「声なき声」にも耳を傾けること。配布後の反応、閲読率、記事の理解度など、さまざまな角度から効果を測定し、次号の改善につなげていきましょう。



PDCAサイクルを意識した継続的な改善が、広報誌の価値を高めていきます
読者の反応を把握
- アンケートの実施
- 感想の収集
- 閲読率の確認
- 配布方法の検証
継続的な改善
- 企画内容の見直し
- デザインの更新
- 読者ニーズの反映
- 制作プロセスの効率化
まとめ:広報誌づくりの3つのポイント
- 読者目線の企画
読者が知りたい情報を、わかりやすく提供することを心がけます - 効率的な制作プロセス
計画的な進行管理と、関係者との密な連携が重要です - 継続的な改善
読者の反応を踏まえ、より良い広報誌へと進化させていきます
広報誌は、学校の「今」を伝える重要なメディアです。
デジタル時代だからこそ、手に取って読める広報誌の価値を再認識し、効果的な活用を目指しましょう!
本特集「教育機関の広報」シリーズで紹介しているさまざまな施策について、客観的に評価・分析できる分析シートを作成しました。無料で提供していますので、ぜひご活用ください。