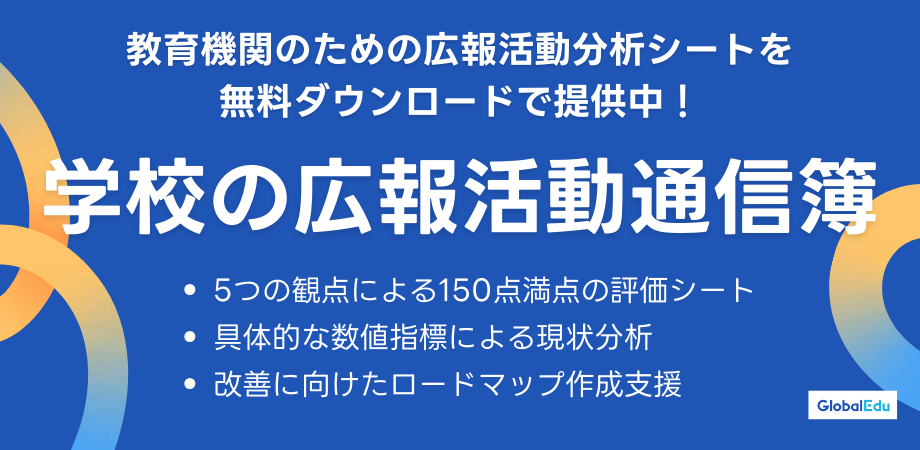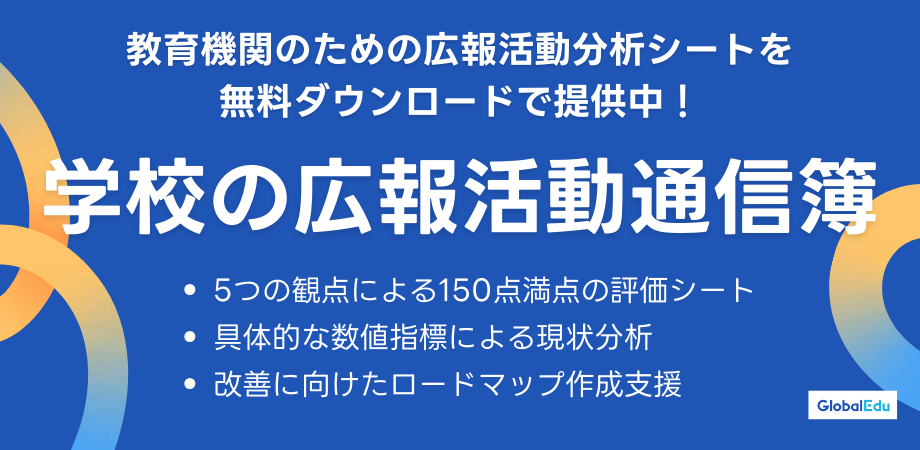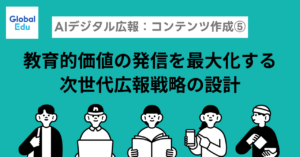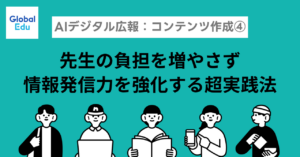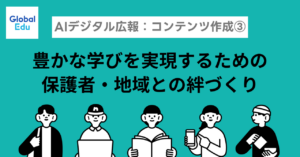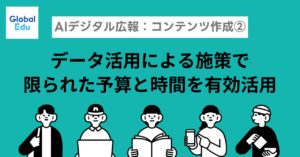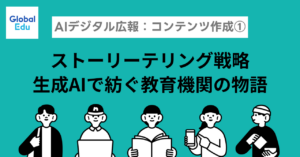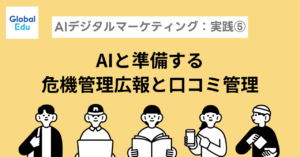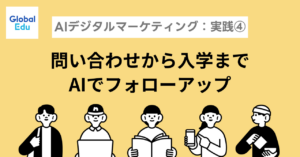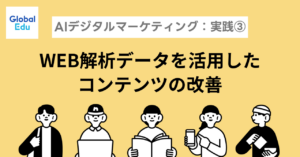Globaleduメルマガでは、広報担当者のみなさんの日々の仕事に役に立つ情報をお届けしています。ぜひご登録ください!
教育機関の広報:実践⑦信頼と絆を深める – 説明会・イベント企画運営ガイド
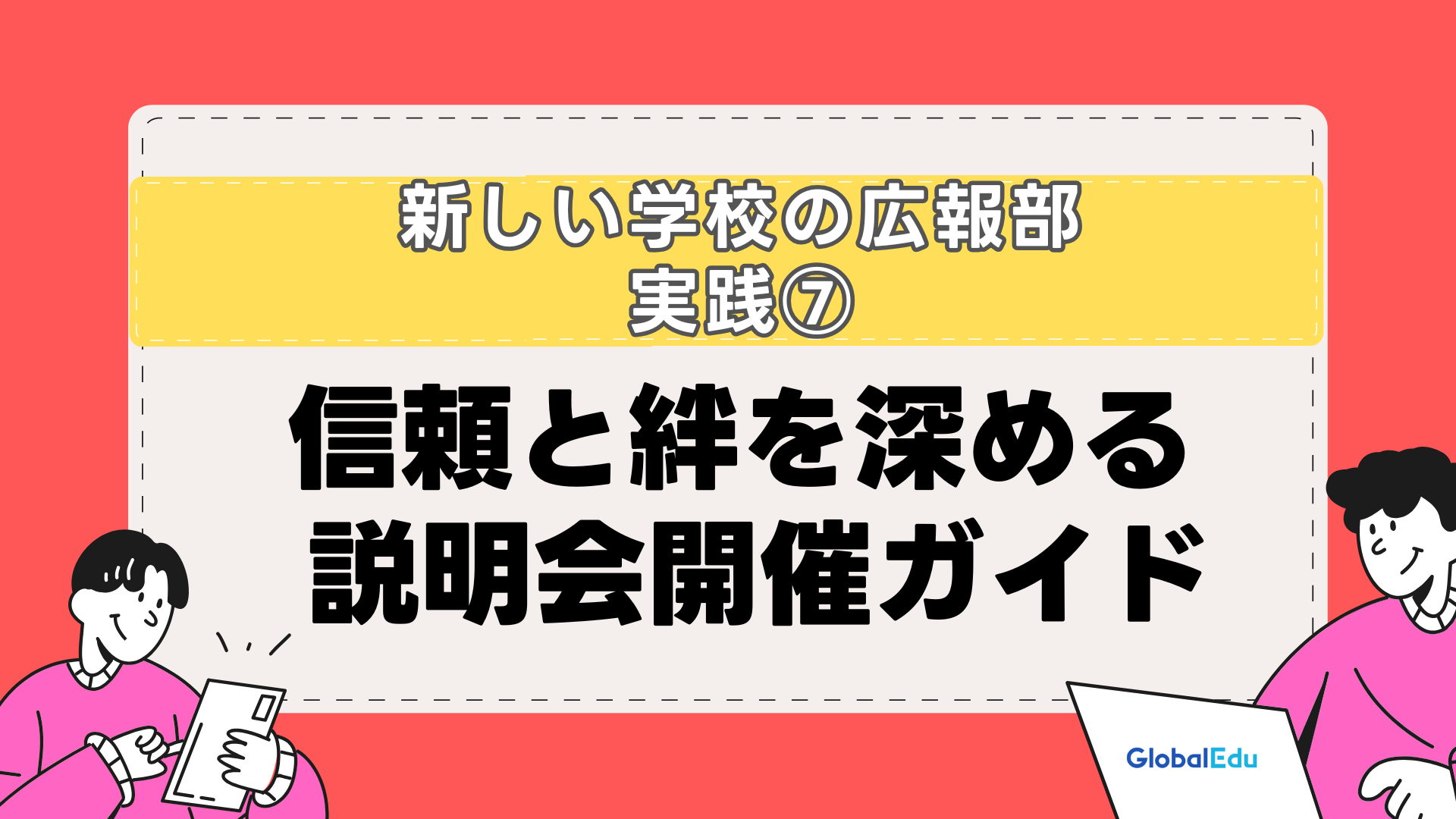
\ 本特集の広報施策を自己評価・分析できる /
理解と信頼を獲得できるイベントを実現しよう
学校説明会やオープンスクールは、学校の魅力を直接伝えられる貴重な機会です。
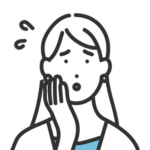 広報担当Aさん
広報担当Aさんでも、説明会やイベントの運営経験が少ないので、スクールの良さを十分に伝えられるか不安…
確かに、大勢の来場者を迎え、限られた時間で学校の魅力を伝えることは、簡単な仕事ではありません。
しかし、説明会やオープンスクールは、Webサイトや広報誌では伝えきれない「学校の空気感」を直接感じてもらえる、とても貴重な機会です。
実際にキャンパスを歩き、スタッフや子どもと接することで、参加者のみなさんはスクールへの理解と信頼を深める機会となります。
本記事では、はじめて説明会やイベントを担当する人にもわかりやすく、企画から運営までのポイントを紹介していきます。
企画の基本的な考え方
説明会やイベントの成功は、企画段階で8割が決まると言っても過言ではありません。とりあえず例年通りではなく、「なぜこのイベントを開催するのか」「誰に何を伝えたいのか」を、しっかりと考える必要があります。
重要なのは、目的とターゲットの明確化です。
オープンスクールなのか、入試説明会なのか、それとも地域交流イベントなのか。参加者はどのような人たちが想定されるのか。
これらを具体的にイメージすることで、効果的なプログラムの設計が可能になります。
目的の明確化
- 学校の特色を理解してもらう
- 受験への意欲を高める
- 保護者の不安を解消する
- 地域との交流を深める
ターゲットの設定
- 学年(小6、中3など)
- 居住地域
- 学力層
- 興味・関心
これらを踏まえて、最適なプログラムを設計していきましょう。
効果的なプログラム設計
説明会やイベントの核となるのが、プログラムの内容です。いくら目的が明確でも、参加者を飽きさせてしまっては、効果は半減してしまいますよね。



大切なのは、限られた時間のなかで「スクールの魅力を最大限に伝えられる構成」を考えることです
タイムスケジュールの組み立て、コンテンツの選定、会場設営まで、すべての要素が参加者の満足度に直結します。
効果的なプログラム例
ここでは、経験豊富なスクールの実例を参考に、効果的なプログラム作りのポイントを紹介します。タイムスケジュールの作り方からコンテンツの工夫、会場設営まで、ぜひ参考にしてみてください。
①タイムスケジュール
学校説明会(2時間)は下記のような構成で行いました。
- 受付(20分)
- 学校紹介(30分)
- 施設見学(30分)
- 体験授業/部活動見学(30分)
- 個別相談(10分)
②コンテンツの工夫
- 在校生による学校紹介
- 実際の授業体験
- 部活動の見学・体験
- 保護者向け個別相談
- 卒業生との交流
③会場設営
- わかりやすい案内表示
- 快適な座席配置
- 展示スペースの確保
- 相談コーナーの設置
- 受付の動線確保
運営のポイント
「素晴らしい企画も、当日の運営次第で台無しになってしまう…」
これは、多くのベテラン広報担当者が口を揃えて言う言葉です。実際、プログラムの内容以上に、運営の良し悪しが参加者の印象を大きく左右します。
とくに重要なのが、来場者への細やかな配慮です。ていねいな受付対応、適切な案内、質問しやすい雰囲気づくりなど、ひとつ一つの対応がスクールの印象となって残ります。
また、暑さ・寒さ対策や休憩時間の確保など、参加者の快適さへの配慮も欠かせません。
このような運営の質を確保するには、スタッフひとり一人の役割を明確にし、チームとして連携することが重要です。
成功に導くための具体的なポイント
①スタッフ体制
各役割の責任者を決め、スムーズな連携を図ります。
- 統括責任者
- 受付担当
- 案内係
- 説明担当
- 相談員
- 撮影係
②参加者への配慮
- ていねいな受付対応
- こまめな声かけ
- 質問しやすい雰囲気づくり
- 休憩時間の確保
- 暑さ・寒さ対策
③情報提供の工夫
- わかりやすい資料作成
- 写真・動画の活用
- デモンストレーション
- 実物の展示
- 体験コーナー
集客のための施策
いい企画を用意しても、参加者が集まらなければ意味がありません。実際、説明会やイベントの参加者数は、スクールの評価に直結する重要な指標となります。
しかし、効果的な告知と適切な特典の設定があれば、参加者数を着実に増やすことは可能です。



大切なのは、「いつ」「どこで」「どのように」情報を届けるかを、ターゲットの行動特性に合わせて考えることです
告知・広報方法について
Webサイトやソーシャルメディアでの告知はもちろん、DMの送付、学習塾への案内、地域への周知など、複数の手段を組み合わせることで、より広い層にリーチすることができます。
- Webサイトでの告知
- SNSの活用
- DM送付
- 学習塾への案内
- 地域への周知
参加特典の検討
また、参加特典の工夫により、来場の動機付けを高めることも効果的です。
- オリジナルグッズ
- 体験授業優待
- 個別相談予約枠
- 記念写真撮影
- 在校生との交流 など
効果測定と改善
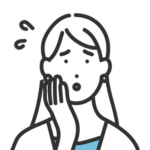
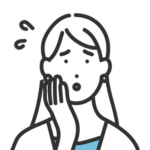
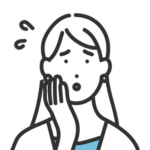
イベントは無事終わったけれど、本当に効果があったのだろうか…
イベントの真の価値は、その後の効果測定と改善活動にこそあります。
アンケートの実施やデータ分析を通じて、参加者の声や行動をていねいにひも解いていくことで、次回への貴重な示唆が得られます。満足度調査はもちろん、改善点の把握、学校への印象変化など、多角的な分析が可能です。
アンケートの実施
- 満足度調査
- 改善点の把握
- 次回参加意向確認
- 学校への印象変化
- 質問・要望の収集
データ分析
また、参加者数の推移や地域別分析、入学率との相関関係など、数値データからも重要な insights が得られます。
- 参加者数の推移
- 地域別分析
- 時期による変動
- 出願率との相関
- プログラム別評価
これらの情報を活用し、継続的な改善を図ることで、より効果的なイベントへと進化させることができます。
フォローアップ
イベント終了後の適切なフォローアップは、参加者との関係を深め、最終的な出願につながる重要なステップです。しかし、多くのケースで、この段階でのアプローチが十分とは言えないのが現状です。



じつは、参加者の心がもっとも学校に向いているのは、イベント直後のこのタイミングです
参加者へのアプローチ
この貴重な機会を活かし、お礼状の送付や追加情報の提供など、きめ細かなコミュニケーションを図ることが重要です。
- お礼状の送付
- 追加情報の提供
- 次回イベントの案内
- 個別相談の提案
- 定期的な情報発信
内部での共有
また、イベントでの学びや気づきをスクール全体で共有し、次回への改善につなげることも欠かせません。
- 実施報告の作成
- 改善点の整理
- 次回への反映事項
- 成功事例の共有
- 課題への対応策
実施報告の作成、改善点の整理、成功事例の共有など、組織的なフォローアップ活動が、より良いイベント運営の基盤となります。
まとめ:成功のための3つのポイント
- 参加者目線の企画
ターゲットのニーズに合わせた、魅力的なプログラムを用意 - 細やかな運営
スタッフひとり一人が、おもてなしの心を持って対応 - 継続的な改善
参加者の声を活かし、より良いイベントへと進化させる
説明会やイベントは、学校の魅力を直接伝えられる貴重な機会です。入念な準備とていねいな運営により、参加者の心に残るイベントを実現しましょう。
本特集「教育機関の広報」シリーズで紹介しているさまざまな施策について、客観的に評価・分析できる分析シートを作成しました。無料で提供していますので、ぜひご活用ください。