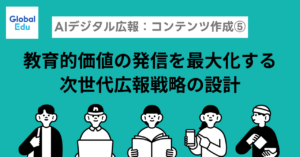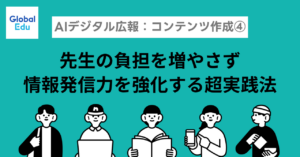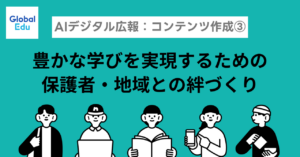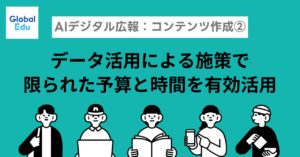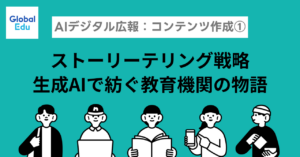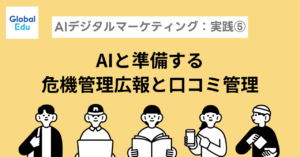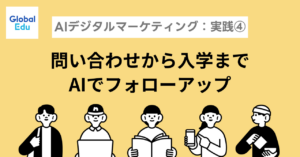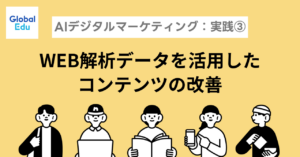Globaleduメルマガでは、広報担当者のみなさんの日々の仕事に役に立つ情報をお届けしています。ぜひご登録ください!
デジタル広報:基礎とAI導入⑤AIで作成したガイドラインでブランディング運用
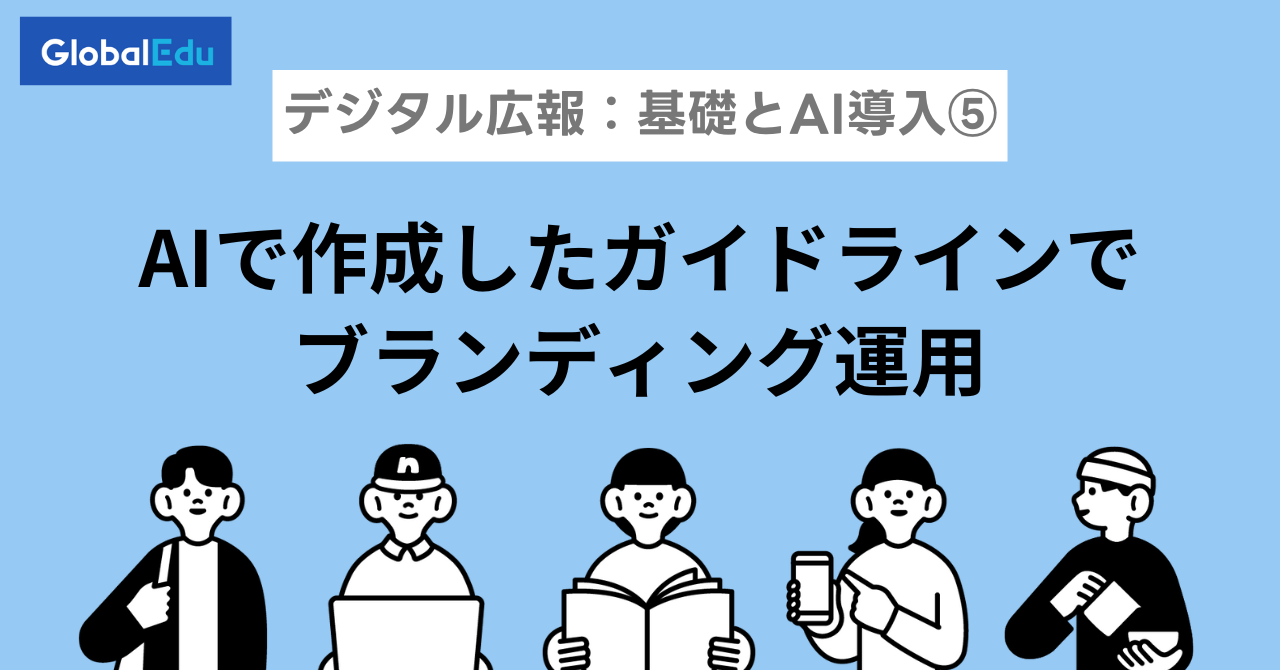
なぜブランドガイドラインが必要か
大阪府のN高校では、以前、こんな課題を抱えていました。
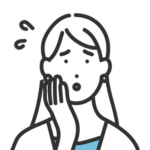 広報担当Aさん
広報担当Aさん進路指導部からの文書は硬い文体、学年便りは柔らかい文体、部活動の連絡は略語が多い。同じ学校からの発信なのに…
また、写真の使い方も部署によってバラバラ。個人情報の取り扱い基準があいまいで、トラブルになりかけたことも。
そこで導入したのが、学校独自のブランドガイドライン。これにより、情報発信の一貫性が保たれ、学校としての一体感が生まれました。
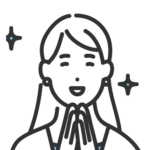
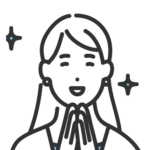
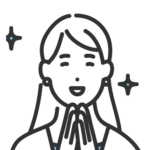
以前は各担当者が手探りで情報を発信していましたが、今は基準が明確になり、新任の先生でも安心して情報発信ができるようになりました
AIを活用したガイドライン作成の利点
従来、ブランドガイドラインの作成には、外部のコンサルタントに依頼するか、担当者が膨大な時間をかけて作成するかの二択でした。
しかし、生成AIを活用することで、学校の特徴や理念を反映した、実用的なガイドラインを効率的に作成できるようになりました。
東京都のO中学校では、ChatGPTを活用してガイドラインの土台を作成。その後、教職員で内容を検討・調整し、2週間ほどで完成にこぎつけました。



AIが提案してくれた項目が、私たちが気づかなかった視点を含んでいて参考になりました。また、文言の使い分けについても、具体的な例を示してくれたので、とても分かりやすかったです
ガイドライン作成の実践的アプローチ
まず、学校の基本情報をChatGPTに入力することから始めます。
本校は創立50年の公立中学校です。教育方針として『自主・協調・創造』を掲げ、少人数制の習熟度別指示と活発な部活動が特徴です。このような学校のブランドガイドライン作成をサポートしてください
すると、AIは以下のような要素を提案してくれます。
基本理念とトーン:
「自主・協調・創造」という教育方針を、日々の情報発信にどう反映させるか。堅すぎず、かつ教育機関としての品位を保つ表現方法。
文体とスタイル:
学内文書、保護者向け文書、地域向け広報、SNSなど、用途別の文体指針。
視覚的要素:
校章の使用規定、写真撮影・掲載の基準、配色の統一基準。
これらの提案を基に、学校の実情に合わせて調整していきます。
成功事例に学ぶ実践のポイント
神奈川県のP小学校では、以下のステップでガイドラインを作成・運用しています。
ステップ1:学校の特徴の言語化
ChatGPTに学校の基本情報を伝え、特徴的な要素を抽出。「温かく、活気があり、地域に根ざした学校」という特徴が浮かび上がりました。
ステップ2:コミュニケーション方針の策定
抽出された特徴を基に、情報発信の基本姿勢を決定。「明るく、わかりやすく、誠実に」という方針に。
ステップ3:具体的なルール作り
文章表現、写真使用、デザイン要素など、具体的なルールを策定。特に気を付けたのは、「誰が担当しても一定の品質を保てる」という点です。
ステップ4:運用テストと改善
まず一部の学年で試験運用を行い、課題を洗い出し。その結果を基にガイドラインを改善しました。
具体的な活用シーン
◉学年便りの作成
ガイドラインに沿った文体で、ChatGPTが文章を生成。担当者は内容の確認と微調整に集中できます。
◉行事案内の作成
定型フレーズや注意事項を統一的に使用。書式も統一されているため、作成時間が大幅に短縮。
◉SNS投稿
学校のトーンや表現方針に沿った投稿文を、AIがサポート。ハッシュタグの選定も一貫性を保てます。
運用時の重要ポイント
◉更新と見直し
ガイドラインは定期的な見直しが重要です。学期ごとに教職員から意見を集め、必要に応じて改訂を行います。
◉新任者への引き継ぎ
異動や新任の教職員にも分かりやすいよう、実例を豊富に含めることがポイント。AIを使って、様々なケースの例文を生成しておくと便利です。
◉臨機応変な対応
非常時や特別な場合の対応も、あらかじめガイドラインに含めておくことで、迷わず適切な対応が可能に。
導入後の変化と効果
Q県のR中学校では、ガイドライン導入後、以下のような変化が見られました:
情報発信の効率化
文章作成時間が約40%短縮。特に、新任の教職員の負担が大きく軽減されました。
保護者からの評価向上
「学校からの情報が分かりやすくなった」「統一感があって読みやすい」という声が増加。
教職員の意識変化
「何をどう伝えるべきか」という基準が明確になり、情報発信への不安が減少。
今日からできること
まずは、現在の情報発信の課題を洗い出してみましょう。「文体の統一」「写真の使い方」「校章の使用規定」など、優先順位の高い項目から始めることをお勧めします。
完璧なガイドラインを一度に作る必要はありません。使いながら改善を重ねていく。それが、持続可能なブランド作りの第一歩となるはずです。



第6回『学校案内・パンフレット制作の新常識』では、企画から制作まで、実践的なノウハウをお届けします