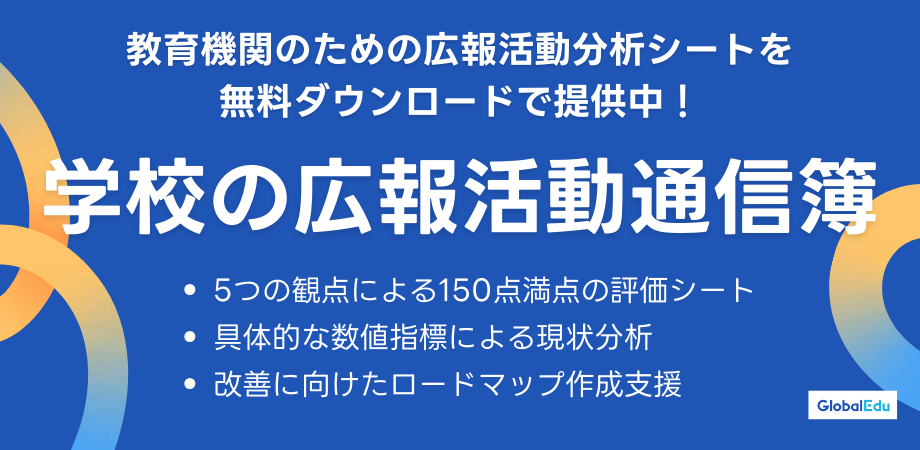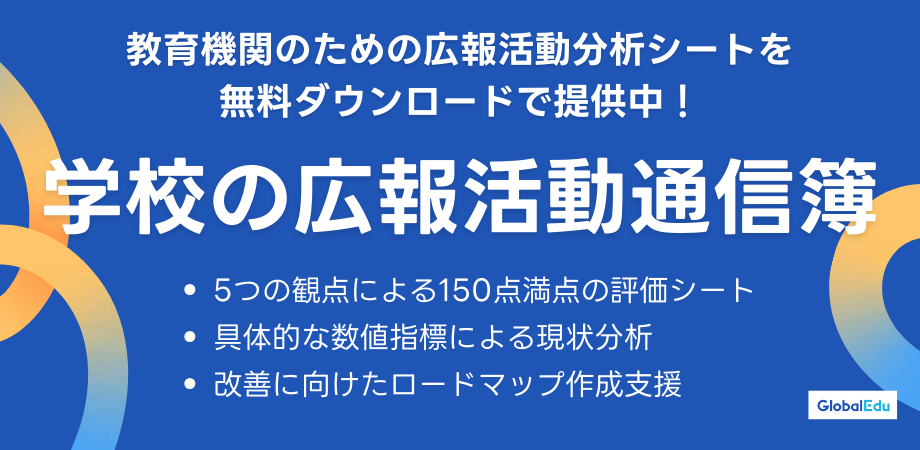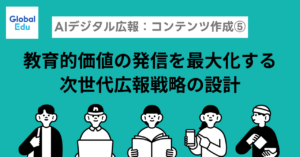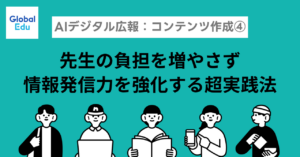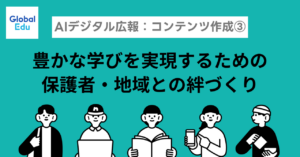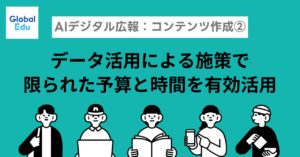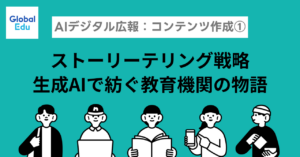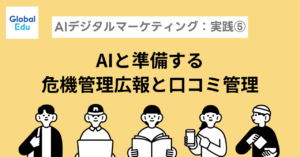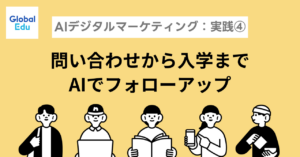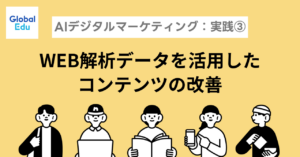Globaleduメルマガでは、広報担当者のみなさんの日々の仕事に役に立つ情報をお届けしています。ぜひご登録ください!
教育機関の広報:施策④学校の信頼を守る – SNS時代の危機管理対応は万全に
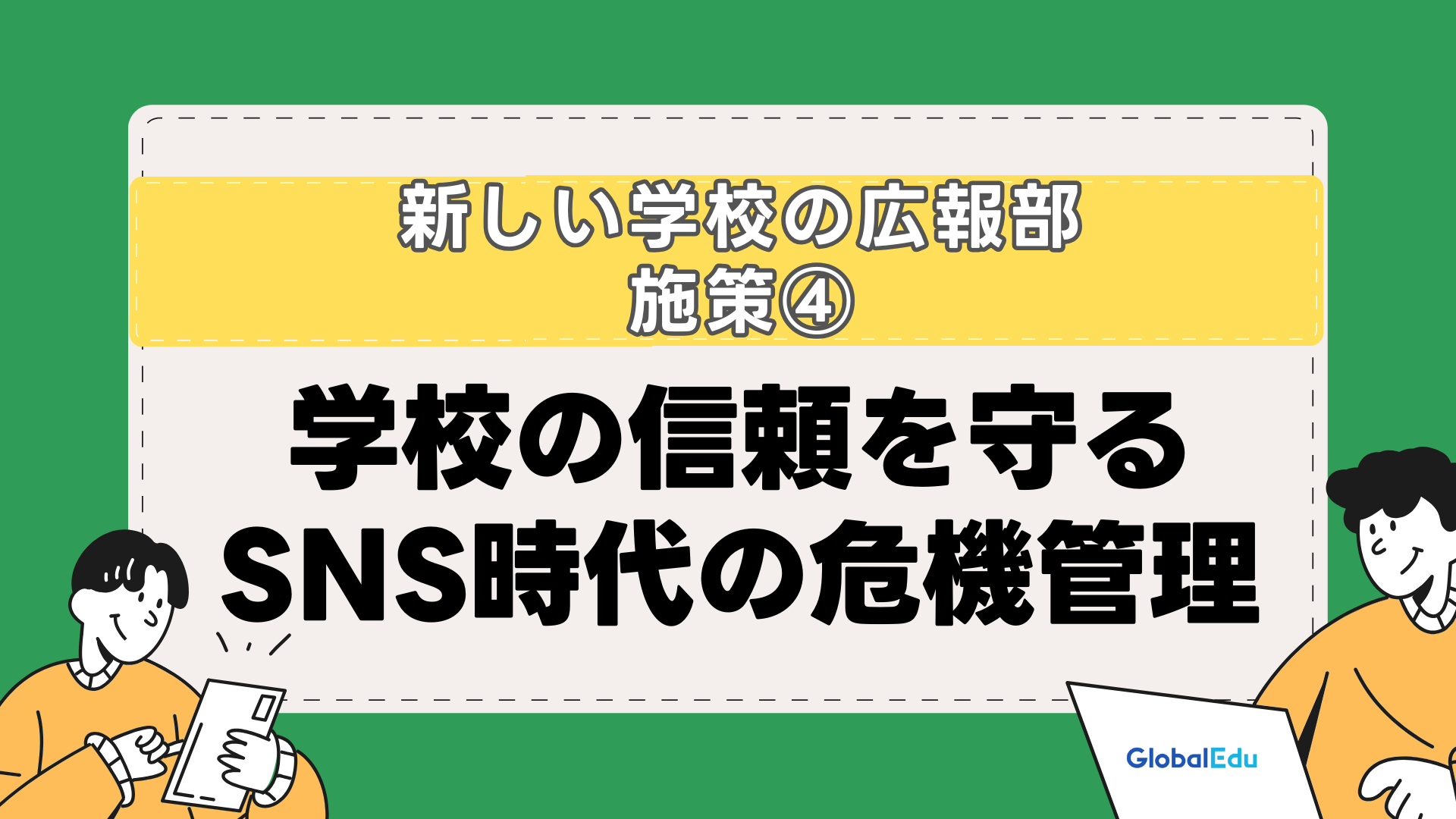
\ 本特集の広報施策を自己評価・分析できる /
「うちの学校は大丈夫」は通用しない時代
SNSの普及により、学校での出来事は瞬時に拡散される時代となりました。
 Globaledu 佐藤
Globaledu 佐藤「うちの学校では大丈夫」と思っていても、予期せぬ事態はいつでも起こりえます
本記事では、実際の教育現場で役立つ危機管理広報の準備方法を紹介します。
スクールの現場で想定される危機
教育現場で起こりうる危機はじつにさまざまです。子どもたちの安全に関わる事故やいじめ問題、教職員の不適切な言動、さらには学校の運営に関する問題まで、幅広い事案があります。
たとえば、休み時間の些細なトラブルが保護者のSNSで拡散され、学校への不信感に発展するケースもあります。
また、スクールスタッフの何気ない発言が、文脈を離れてひとり歩きしてしまうこともあります。このような事態に備えて、想定される危機を具体的にリストアップし、対応策を考えておくことが重要です。
平時からの備え
「備えあれば憂いなし」という言葉のとおり、危機管理でもっとも重要なのは平時からの準備です。
①危機管理マニュアルの整備
マニュアルは、緊急時のバイブルとなります。ただし、分厚すぎて誰も読まないようなものでは意味がありません。実際に使える、簡潔で具体的なマニュアルを作成しましょう。
とくに重要なのは、「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかを明確にすることです。また、定期的な更新と見直しも欠かせません。
社会環境の変化や新たなリスクに応じて、柔軟に内容を更新していく必要があります。
②広報体制の構築
いざというときに慌てないよう、あらかじめ役割分担を決めておくことが重要です。
校長を統括責任者とし、広報責任者、情報収集担当、SNS対応担当など、具体的な役割を決めておきましょう。
また、定期的な研修や訓練も欠かせません。
とくにメディア対応については、実践的なトレーニングを行うことをお勧めします。想定される質問への回答や、適切な情報開示の範囲について、事前に確認しておくことが大切です。
③情報発信の準備
緊急時に必要となる情報発信ツールは、すぐに使える状態で整備しておく必要があります。とくに緊急連絡網は、定期的に更新し、実際に機能するかテストしておくことが重要です。
プレスリリースの雛形やWebサイトの更新手順なども、誰でも使えるように整理しておきましょう。SNSについては、普段から適切な運用ルールを定め、スタッフ間で共有しておくことが大切です。
危機発生時の対応
実際に危機が発生した際は、迅速かつ適切な対応が求められます。時間の経過とともに必要な対応を説明します。
①初動対応(30分以内)
危機発生直後の30分は非常に重要です。この時間で、正確な情報収集と初期対応の方向性を決定する必要があります。
まずは事実確認を行い、対策本部を設置します。関係者への第一報も忘れずに行いましょう。
②基本方針の決定(2時間以内)
初期情報を整理し、対応方針を決定する段階です。
とくに情報開示の範囲については慎重に検討が必要です。必要以上の情報を出すことで混乱を招くことも、情報不足で不信感を生むことも避けなければなりません。
③情報発信(24時間以内)
方針が決まったら、速やかに情報発信を行います。
保護者への連絡、プレスリリース、Webサイトの更新など、さまざまなチャネルを通じて適切に情報を発信していきます。
効果的な情報発信のポイント
①メッセージの基本原則
情報発信では、「正確・迅速・誠実」が基本となります。
事実と異なる情報を発信すると、取り返しのつかない信頼低下を招きかねません。不確かな情報については、「現在確認中」と正直に伝えることが重要です。
②関係者ごとの対応
生徒・保護者、スクールスタッフ、地域社会など、それぞれに適した情報発信が必要です。相手の立場や不安に配慮した、きめ細かな対応を心がけましょう。
まとめ:今日からできる準備
危機管理広報の準備は、今日から始めることができます。



まずは、想定される危機をリストアップし、必要な対応を考えていきましょう
すべてを一度に整備する必要はありません。できることから少しずつ、着実に準備を進めていくことが大切です。
次回は、スクールの強みと価値を伝える「ブランディング戦略」について解説します。
本特集「教育機関の広報」シリーズで紹介しているさまざまな施策について、客観的に評価・分析できる分析シートを作成しました。無料で提供していますので、ぜひご活用ください。