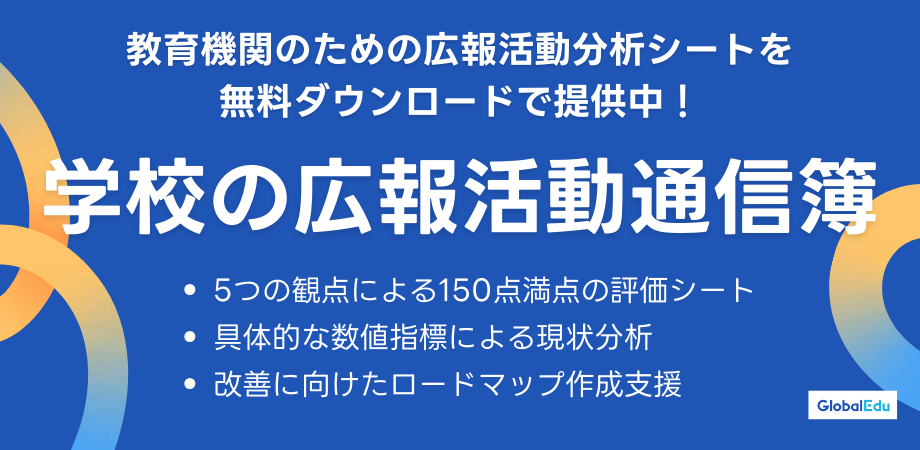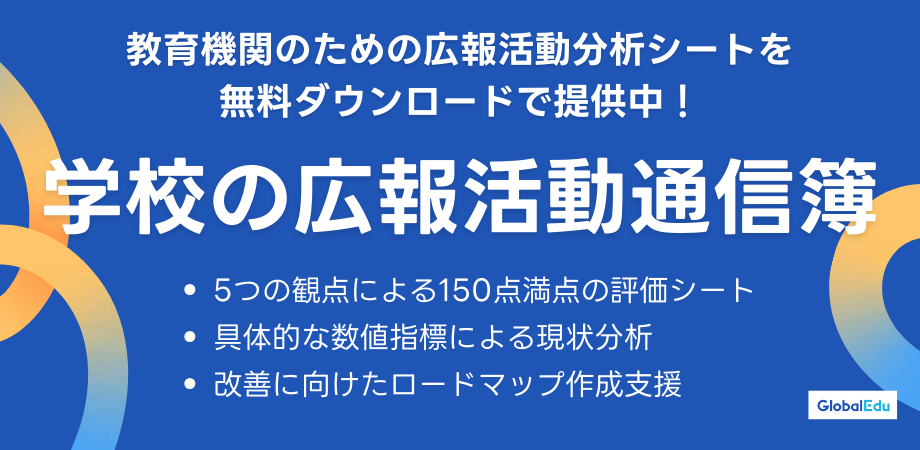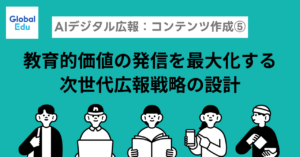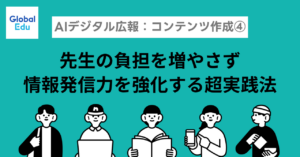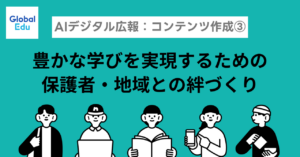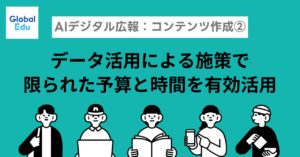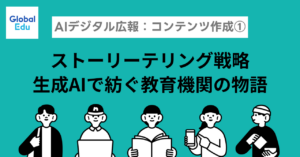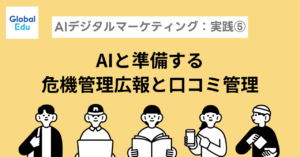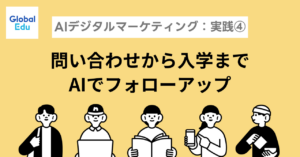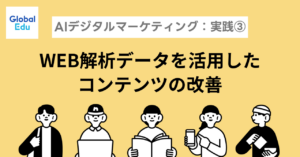Globaleduメルマガでは、広報担当者のみなさんの日々の仕事に役に立つ情報をお届けしています。ぜひご登録ください!
教育機関の広報:実践①効果的なプレスリリースを書くための10のテクニック
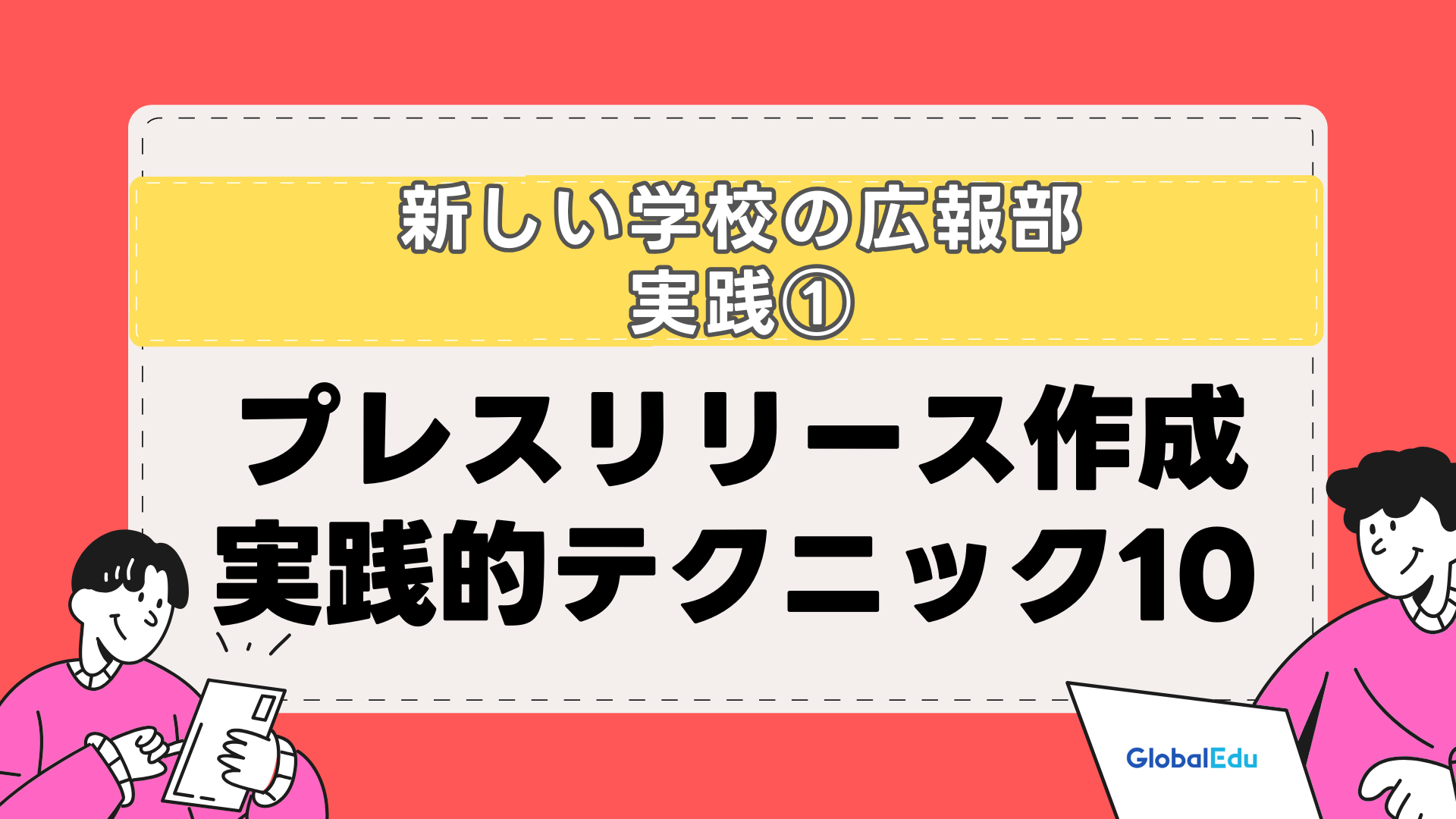
\ 本特集の広報施策を自己評価・分析できる /
効果的に伝えるための10のテクニック
教育現場での取り組みを、効果的にメディアに伝えるのがプレスリリースです。
効果的なプレスリリースを発信することで、スクール取り組みを社会に広く知ってもらうことが可能です。
 Globaledu 佐藤
Globaledu 佐藤その作成のコツを、10の実践的なテクニックで紹介していきます
テクニックを紹介したあとは、テンプレートも紹介するので、ぜひ活用してくださいね。
① 見出しは「新規性」と「社会性」を意識する
「〇〇スクール、県内初のAIプログラミング講座をスタート」のように、新しい取り組みが社会にどのような価値をもたらすのかを、端的に表現します。
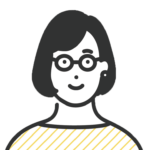
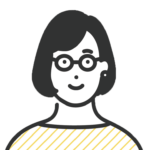
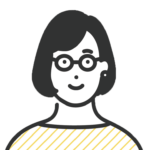
重要なのは、教育現場の視点だけでなく、社会の関心事との接点を見つけることです
②リード文は5W1Hを簡潔に
最初の段落で、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、いつ(When)、どこで(Where)、どのように(How)実施するのかを明確に説明します。
ただし、詳細は本文で説明するため、ここでは要点のみを押さえます。
③数字を効果的に活用する
「生徒の英語力が向上」ではなく、「英検合格率が前年比2倍」のように、具体的な数字で表現することで、説得力が増します。
ただし、数字の羅列は避け、もっとも印象的な数値を選んで使用することで印象を強くさせます。
④ストーリー性を持たせる
なぜその取り組みを始めたのか、どのような課題を解決したいのか、そしてどのような成果が期待されるのか。時系列に沿って、物語として展開することで、読み手の関心を引きつけます。
⑤キーパーソンの声を引用する
生徒、スタッフ、保護者など、実際の声を引用することで、取り組みの意義や効果がより生き生きと伝わります。とくに、具体的なエピソードを交えた感想は、記事化されやすい要素となります。
⑥写真・図表を効果的に活用する
「百聞は一見にしかず」のとおり、適切な視覚資料は情報の理解を助けます。ただし、画質の良い写真を2〜3枚程度に絞り、それぞれにキャプションをつけることが重要です。
⑦専門用語をわかりやすく説明する
教育現場特有の用語は、一般の読者には分かりにくいものです。「アクティブラーニング」を「生徒が主体的に参加する学習方法」のように、平易な言葉で説明を加えます。
⑧ 社会的な文脈を示す
その取り組みが、なぜいま、社会的に意味があるのかを説明します。たとえば、SDGsやデジタル化など、現代の課題との関連性を示すことで、ニュース性が高まります。
⑨今後の展望を示す
単発の取り組みで終わるのではなく、将来的にどのように発展させていくのか、どのような効果が期待されるのかを具体的に示します。これにより、継続的な報道につながる可能性が高まります。
⑩ 問い合わせ先を明確に
記者から追加取材の依頼があった際に、スムーズに対応できるよう、担当者の連絡先を明記します。可能な限り、携帯電話番号やメールアドレスなど、直接連絡が取れる手段を提供することが望ましいです。
実際のテンプレートと作成例
いますぐ使えるテンプレート
[発表日]
【見出し】
新規性と社会性を端的に表現
【サブタイトル】
補足説明を1行で
【リード文】
第一段落で5W1Hを簡潔に説明
【本文】
- 背景・課題
社会的な文脈や必要性を説明 - 取り組みの詳細
具体的な内容を説明 - 期待される効果
数値目標や具体的な成果 - 関係者の声
生徒・教員・保護者の声を引用 - 今後の展望
将来的な発展性を示す
【写真】
・写真1:活動の様子
・写真2:関係者の集合写真など
【問い合わせ先】
担当者名:
所属・役職:
TEL:
Email:
作成例をチェック
2025年1月25日
【見出し】
県内初、全校生徒にAIリテラシー教育を必修化
〜地域企業と連携し、実践的なプログラミング教育を展開〜
【リード文】
私立○○高等学校(校長:山田太郎)は、2025年4月より、全学年でAIリテラシー教育を必修科目として導入します。地域のIT企業5社と連携し、実践的な課題解決型学習を展開することで、次世代のデジタル人材育成を目指します。
【本文】
■背景
デジタル社会の進展に伴い、AI・プログラミングの基礎知識は、あらゆる職業で必要とされています。しかし、実践的なAI教育を実施している高校は全国でもわずか5%に留まっています。
■取り組みの詳細
・週1回の必修授業(年間35時間)
・地域IT企業によるワークショップ(月1回)
・実際の業務課題を教材として活用
・生徒が開発したアプリの実用化を目指す
■期待される効果
・IT関連進学率30%増加
・地域企業でのインターンシップ受入100名
・実践的なデジタルスキルの習得
■生徒の声
情報処理部3年生 佐藤花子さん
「実際の業務課題に取り組むことで、プログラミングの実践的な活用方法を学べています。将来はIT企業でAI開発に携わりたいと考えるようになりました」
■今後の展望
2026年度には、地域の中学生向けプログラミング教室の開催も計画しています。地域全体のデジタルリテラシー向上に貢献していきます。
【写真】
写真1:プログラミング授業の様子
写真2:企業との連携プロジェクト発表会
【問い合わせ先】
担当:教頭 鈴木一郎
TEL:xxx-xxxx-xxxx
Email:xxxxx@xxx.xx.xx



10のテクニックを意識しながら、スクールの魅力を効果的に伝えていきましょう!
本特集「教育機関の広報」シリーズで紹介しているさまざまな施策について、客観的に評価・分析できる分析シートを作成しました。無料で提供していますので、ぜひご活用ください。